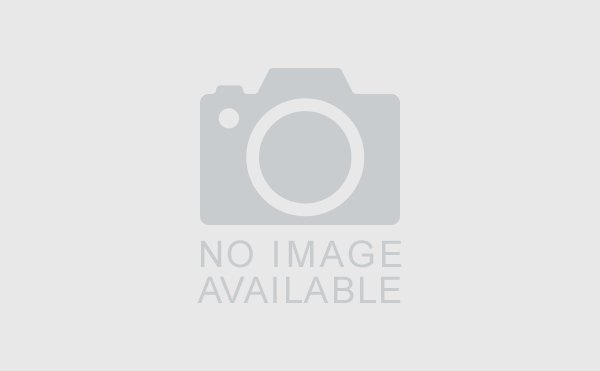梅雨の養生
梅雨の不調、もしかして「湿邪」?
6月を迎え、いよいよ梅雨の季節となります。気温の変化には注意を払う方が多いものの、意外にも対策が疎かになりがちなのが「湿度」です。しかし、東洋医学において、この時期の過剰な湿気は 「湿邪(しつじゃ)」 と呼ばれ、様々な体調不良の原因となると考えられています。
湿度と体調不良の関係性
東洋医学では、自然界の余分な水分が体内に侵入することで、様々な不調を引き起こすと捉えます。梅雨はまさに湿邪が勢いを増す時期であり、以下のような症状が現れやすくなります。
- 倦怠感、疲労感
- 頭重
- 関節痛
- 食欲不振、胃もたれ
- 浮腫(むくみ)
- 下痢傾向
これらの症状は明確な原因がわからないままやり過ごされがちですが、背景には湿邪の影響が潜んでいる可能性があります。
湿邪から身を守るための日常ケア
湿邪による不調を予防するためには、日々の生活の中でいくつかの点に注意することが大切です。
- 室内の除湿
- エアコンや除湿機を活用し、室内の湿度を適切に管理しましょう。昼間の活動時だけでなく、睡眠時も大事です。睡眠中は体内の活動が緩やかになり、水分代謝も停滞しやすくなります。 翌朝のむくみや抜けない疲れを感じる場合は、寝室の除湿にも気を配ってみてください。
- 保温
- 冷たい飲食物は控え、内臓を冷やさないように注意しましょう。冷えは体内の水分代謝を滞らせ、湿邪を蓄積しやすくします。
- 入浴はシャワーだけでなく、湯船に浸かり体を温めることが望ましいです。発汗は余分な水分を排出する有効な手段です。
- 適度な運動
- 軽い運動は血行を促進し、体内の水分循環を改善します。
- 天候に左右されにくい室内での運動も取り入れると良いでしょう。
- 食養生
- ハトムギ、小豆、トウモロコシなど、利水作用のある食材を積極的に摂取しましょう。
- 消化に負担のかかる生ものや脂質の多い食品は、水分を溜め込みやすいため、摂取を控えめにしましょう。
漢方薬によるアプローチ
体質や具体的な症状によっては、漢方薬が有効な選択肢となる場合があります。
- 五苓散(ごれいさん): 水分の偏在によるめまい、嘔吐、浮腫などに用いられます。
- 六君子湯(りっくんしとう): 胃腸が弱く、食欲不振や胃もたれがあり、疲れやすい方に向いています。
漢方薬の使用にあたっては、専門家である医師や薬剤師に相談することが重要です。有恒薬局では、皆様の体質や症状に合わせた漢方薬や養生法をご提案しております。どうぞお気軽にご相談ください。
梅雨の時期を健やかに過ごすためには、湿度への対策も重要な要素です。日々のケアと必要に応じた漢方薬の活用で、 ジメジメした季節を快適に乗り切りましょう!