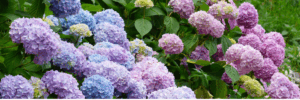相生・相剋関係
5月5日の端午の節句の由来は、2300年前の中国の楚という国に、民衆から慕われ忠誠心の高い屈原という詩人が、陰謀によって国を追われる際に国の行く末に失望して川に身を投げてしまったことにあります。その時に民衆は川にチマキを投げ入れて魚に屈原が食べられないようにしたことから、屈原が入水した5月5日に忠義のある子に育つことを願い、子供にちまきを食べさせる風習が生まれました。それが中国全土に広がり、やがて日本にも伝来したということです。さらに5月5日に飾る鯉のぼりの吹き流しは五色(青・赤・白・黒・黄)の魔除けの意味を持っています。五色は五行説の季節に由来していて、春・夏・秋・冬・土用を表しています。吹き流しを飾ることで、これら五つの要素が全ての季節を守ってくれて、邪気を払ってくれると考えられていたそうです。
さて、五行のお話の続きですが木・火・土・金・水の五つの要素はバランスを保つ為に2つの関係を持っています。1つ目が相生関係という成長を促進する関係です。イメージとしては、「木はこすれあって火を生み、火は燃えて灰となり肥沃な土(大地)を生み、大地は地殻変動で金(鉱物)を生み、鉱物はミネラル豊かな水を生む、この水は木を育む」という木→火→土→金→水→木という助ける関係性です。
もう一つが相剋関係という成長を抑制する関係です。「木は土の養分を吸い取り、火は金(金属)を溶かし、土は水を堰き止め、金(金属)は斧の様に固くなり木を切り裂く、水は火を消す。」というブレーキをかけるような関係性です。この2つの関係を基に病気を未然に防ぐのが薬膳の教えです。酸味(木)をとり過ぎると脾胃(土)の働きを阻害するため、甘味(土)を組み合わせて脾胃を補う、これは甘酢などに当てはまりますね。相生・相剋でバランスを取る、お食事はもちろん他の場面でも役に立つ漢方の考えです。